脳神経外科
脳神経外科の紹介
当院の脳神経外科は1976年に開設され、以来西濃医療圏で24時間365日対応可能な脳神経外科施設として皆様の診療にあたってきました。救急救命センターへ入院される脳卒中(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞)、頭部外傷をはじめとする救急疾患ばかりでなく、脳腫瘍、脊椎脊髄疾患、水頭症、小児脳神経外科疾患など脳神経疾患に対して幅広く対応しています。
脳神経外科の基本方針
安全な医療を最優先に患者さん中心の医療を心がけています。脳腫瘍の手術では脳神経外科手術用ナビゲーションシステムや術中電気生理学的モニターを活用して術後の合併症を防げるようにしています。下垂体手術には神経内視鏡を使用して低侵襲の手術に努めています。ガンマナイフなどの定位放射線治療が必要な脳腫瘍の患者さんには、術後ガンマナイフのある病院へご紹介させて頂いております。近年血管内手術がめざましく発達してきております。当院では脳動脈瘤の手術に際しては開頭術と血管内手術、それぞれの適性を考慮して個々の症例に対して最適な治療を選択して提供しています。
脳卒中や頭部・脊髄外傷後の高度痙縮によりQOLが低下している患者さんに対して内服加療で効果が不充分な場合には脊髄への薬剤の持続注入治療(ITB療法)やボトックス治療を行っています。
スタッフ紹介
- 槇 英樹

| 役職 | 脳神経外科 主任部長 |
|---|---|
| 卒業大学名 医師免許取得年 |
自治医科大学 1990年 |
| 専門医資格(その他) | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本神経内視鏡学会技術認定医 日本臨床神経生理学会 |
| 専門分野 | 脳腫瘍、頭蓋底手術 内視鏡手術 |
- 野田 智之

| 役職 | 脳神経外科 部長 |
|---|---|
| 卒業大学名 医師免許取得年 |
金沢大学 2000年 |
| 専門医資格(その他) | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脊髄外科学会 |
| 専門分野 | 脳血管障害の外科的治療 背髄疾患治療 |
- 今井 資

| 役職 | 脳神経外科 医長 |
|---|---|
| 卒業大学名 医師免許取得年 |
筑波大学 2008年 |
| 専門医資格(その他) | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医・指導医 日本脳卒中学会専門医・指導医 |
| 専門分野 | 脳血管内治療 |
- 川端 哲平

| 役職 | 脳神経外科 医長 |
|---|---|
| 卒業大学 医師免許取得年 |
名古屋大学 2010年 |
| 専門医資格(その他) | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本内分泌学会内分泌代謝科専門医 日本脳卒中学会専門医 日本神経内視鏡学会技術認定医 脳血栓回収療法実施医 |
| 専門分野 | 内視鏡手術 |
- 左合 央明
| 役職 | 医員 |
|---|---|
| 卒業大学名 医師免許取得年 |
名古屋大学 2022年 |
| 専門医資格(その他) | |
| 専門分野 | 一般脳神経外科 |
- 渡邊 幸美
| 役職 | 医員 |
|---|---|
| 卒業大学名 医師免許取得年 |
名古屋大学 2022年 |
| 専門医資格(その他) | |
| 専門分野 | 一般脳神経外科 |
- 森田 翔
| 役職 | 医員 |
|---|---|
| 卒業大学名 医師免許取得年 |
名古屋大学 2023年 |
| 専門医資格(その他) | |
| 専門分野 | 一般脳神経外科 |
診療実績
脳神経外科の2022年の入院患者数は848人、手術件数は355件、病棟病床数は31ですが救急救命センターや集中治療室の病床も利用しています。
| 入院患者疾患 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳腫瘍 | 57 | 73 | 82 | 117 | 78 |
| 脳動脈瘤 | 61 | 61 | 55 | 86 | 84 |
| 脳出血 | 184 | 182 | 152 | 178 | 171 |
| 閉塞性脳血管障害 | 187 | 192 | 187 | 99 | 72 |
| 頭部外傷 | 213 | 269 | 304 | 270 | 225 |
| 脊椎・脊髄疾患 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| その他 | 137 | 102 | 71 | 106 | 77 |
| 総計 | 848 | 886 | 855 | 858 | 712 |
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|
| 手術 | 355 | 384 | 388 |
| 脳動脈瘤手術 | 46 | 37 | 41 |
| 開頭動脈瘤クリッピング術 | 28 | 25 | 28 |
| (high flow bypass) | (0) | (2) | (0) |
| 動脈瘤コイル塞栓術 | 18 | 12 | 13 |
| 脳腫瘍手術 | 29 | 49 | 56 |
| 神経膠腫(膠芽腫など) | 7 | 10 | 6 |
| 髄膜腫 | 4 | 10 | 13 |
| (頭蓋底髄膜腫) | (2) | (3) | (6) |
| 下垂体腫瘍(経鼻内視鏡手術) | 5 | 10 | 10 |
| 頭蓋咽頭腫 | 2 | 2 | 2 |
| 聴神経腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
| 悪性リンパ腫 | 5 | 7 | 2 |
| そのほかの原発性脳腫瘍 | 4 | 2 | 7 |
| 転移性脳腫瘍 | 1 | 8 | 15 |
| 頭蓋骨腫瘍摘出術 | 3 | 0 | 1 |
| 脳出血手術 | 15 | 24 | 20 |
| 開頭血腫除去術 | 3 | 9 | 12 |
| 内視鏡下血腫除去術 | 12 | 15 | 8 |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 5 | 3 |
| 頸動脈狭窄症手術 | 22 | 13 | 18 |
| 頸動脈内膜剥離術(CEA) | 8 | 5 | 6 |
| 頸動脈ステント留置術(CAS) | 14 | 8 | 12 |
| 浅側頭動脈・中大脳動脈吻合術 | 0 | 3 | 1 |
| 血栓回収療法 | 31 | 31 | 34 |
| 硬膜動静脈瘻塞栓術 | 4 | 4 | 4 |
| その他の血管内手術 | 4 | 1 | 3 |
| 頭部外傷手術(開頭血腫除去術) | 15 | 16 | 15 |
| 急性硬膜下血腫 | 8 | 7 | 10 |
| 急性硬膜外血腫 | 4 | 4 | 2 |
| 脳挫傷 | 3 | 5 | 3 |
| 微小血管減圧術 | 4 | 2 | 1 |
| 顔面けいれん | 2 | 1 | 1 |
| 三叉神経痛 | 2 | 1 | 0 |
| 水頭症手術 | 12 | 21 | 19 |
| 脳室・腹腔短絡術(V-Pシャント) | 10 | 20 | 19 |
| 第3脳室底開窓術(ETV) | 2 | 1 | 0 |
| 脊髄腫瘍手術 | 1 | 0 | 0 |
| 小児奇形手術 | 1 | 0 | 0 |
| 慢性硬膜下血腫手術 | 148 | 119 | 129 |
| 脳室ドレナージ術 | 13 | 14 | 8 |
| その他 | 6 | 45 | 35 |
論文と学会発表
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学会発表数 | 12 | 15 | 11 | 16 | 15 |
| 論文数 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| 著書数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
治療について
脳血管障害
【脳卒中診療】
脳卒中には血管が破綻して起こる出血性脳卒中(くも膜下出血、脳出血)と閉塞あるいは狭窄して起こる虚血性脳卒中(脳梗塞)に分けられます。

当院では、「(最新版)脳卒中治療ガイドライン」に準拠し、開頭手術、脳血管内手術、内視鏡手術を適切に組み合わせて治療を行っています。当院は西濃医療圏唯一の一次脳卒中センターコア施設(PSCコア:Primary Stroke Center)を日本脳卒中学会より認定されており、すべての脳卒中患者さんにより適切な治療を提案しています。
<出血性脳卒中>
・くも膜下出血
多くの場合、脳動脈瘤破裂により起こります。再破裂予防、脳血管攣縮、水頭症と乗り越えなければならない壁があります。動脈瘤破裂の場合、再破裂予防として開頭手術(開頭脳動脈瘤クリッピング手術)と血管内手術(脳動脈瘤コイル塞栓術)があります。当院では、未破裂脳動脈脈瘤同様に、患者さんの状態、動脈瘤の形状など総合的に判断し適切な治療法を選択します。当院では年間40-60件の破裂脳動脈瘤の治療をしております。近年ではカテーテル治療が増加していますが、通常の開頭クリッピング術のみならず、複雑な病態でバイパス併用手術など難易度の高い手術も対応しています。

・脳出血
高血圧などが原因となることが多く、脳の圧迫が強い場合や脳の中の水(髄液)の流れが悪い場合(水頭症)は手術が必要となることがあります。圧迫している血腫を取り除く手術には開頭手術と内視鏡手術があり、状態に応じて使い分けで管理をしています。併せて水頭症を合併している症例に対してはドレーンを挿入し、救急病棟で厳密な管理を行なっています。

また、出血原因が異常血管(脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻、動脈瘤など)による場合は、再出血予防のために開頭手術(顕微鏡手術)、血管内手術、内視鏡手術を組み合わせて行うこともあります。
<虚血性脳卒中>
・脳梗塞
症状が強く発症から時間の経過していない症例ではt-PA静注療法という強力な血栓溶解療法、また脳の太い血管が閉塞した重症脳梗塞についてはカテーテルで閉塞部位を開通させる治療(機械的血栓回収療法)を行うことで症状の急速な改善が得られる場合があり、適応となる症例は遅滞なく、24時間365日行うことができる体制を整えています。これらの特殊な治療が適応となる脳梗塞は脳神経外科を中心として管理を行なっています。一方、これらの特殊な治療が適応とならない内科的管理が中心となる脳梗塞は内科を中心として管理を行なっています。

いずれの脳卒中の病態においても治療管理はチーム全体で管理し、早期にリハビリテーションを行い、より患者さんの神経予後に改善できるよう管理を行なっています。また、急性期加療終了後、スムーズに在宅や回復期リハビリテーション病院に移行出来るよう周辺の医療機関とも密に連携をとっています。脳卒中に関するご相談はよろず相談所に脳卒中相談窓口設けておりますのでお気軽にご相談ください。
【未破裂脳動脈瘤】
動脈瘤が破裂をすると、くも膜下出血となります。破裂リスクの高い方は破裂前に予防的な治療を提案することがあります。当院では脳卒中ガイドラインに準拠し、治療について御本人、御家族と話し合い行い、決めています。具体的には5mm以上、増大傾向など患者さんの年齢や状態を十分に検討し、外科的治療を提案します。治療法は開頭術、カテーテル手術について科内で各領域の専門医/指導医が十分な検討の上、どちらの治療法に優位性があるかを協議した上で、患者さんの意向も踏まえて方針を決定しています。手術を行わない場合は自然歴による破裂リスクなどを説明、ご理解頂いた上、定期的に画像検査を行なっています。
【頚動脈狭窄症】
脳にいく頚部の血管(内頚動脈)が細くなり、その遠位の血流が低下することで脳梗塞、一過性脳虚血発作(一時的な麻痺や話しにくさなど)、黒内障(急に目が見えなくなる)の原因となる場合があります。これらの再発予防のため頚動脈頚動脈の治療を行う場合があります。これには手術による方法(内頚動脈内膜剥離術)とカテーテル治療(頚動脈ステント留置術)があります。それぞれに長所と短所があり当院では熟練した各領域の専門医で協議の上、患者さんの意向も踏まえて治療法を決定しています。

【閉塞性血管障害】
頭蓋内血管が閉塞し、脳梗塞や一過性脳虚血発作を引き起こす疾患(内頚動脈/中大脳動脈閉塞症、もやもや病など)で内科的治療より外科的加療が望ましい場合はバイパス手術を提案しています。
【硬膜動静脈瘻】
脳や脊髄の周囲の構造物(骨や硬膜)を栄養する血管が、主に静脈洞という硬膜に囲まれ脳で使用された血液が通る太い通り道と交通してしまう疾患です。耳鳴り程度の症状からしびれ、眼球突出、痙攣、脳出血、など重篤な症状を引き起こすものまで様々です。脳や脊髄、目の血管に逆流を起こしている場合、神経症状を伴う場合は治療を検討します。多くの場合、血管内手術で行いますが、部位によっては開頭術を行います。比較的稀な疾患です。

【脳動静脈奇形】
脳の動脈と静脈が細かな血管を介して直接吻合した病態です。若年脳出血の原因となることが多いと言われています。年齢や病変の部位、サイズから、経過観察とする場合も多いですが、治療の場合は開頭術、血管内手術、放射線手術を組み合わせて適切な治療方法を検討します。
◉脳腫瘍
良性から悪性まで様々な腫瘍に対して手術治療及び後療法(化学療法、放射線療法)を行なっています。手術においては最新の手術顕微鏡や神経内視鏡を用い、手術ナビゲーションシステム、蛍光色素、神経電気生理学的モニタリングなど最新機器を使用して安全な手術を心掛けています。手術のみならず悪性脳腫瘍の標準的な化学療法、放射線治療も行っております。また当院には日本神経内視鏡学会技術認定医が2名おり、特に経鼻下垂体手術など内視鏡を用いた手術にも力を入れています。患者さんの年齢、状態、腫瘍の種類などによっては基幹病院である名古屋大学と連携し、紹介を行うこともあります。

◉頭部外傷について
年齢を問わず軽症から重症全ての頭部外傷に対して内科的治療から外科的治療まで対応しています。重症頭部外傷では日本神経外傷学会編集「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン」に準拠して治療を行なっており、緊急手術にも迅速に対応できる体制を整えています。
◉その他
顔面痙攣や三叉神経痛で難治性や薬剤抵抗性の場合、また患者さんの年齢や状態によって、外科的手術が望ましい患者さんの場合、外科的手術(微小血管減圧術)を提案しています。また、脊髄腫瘍や脊髄血管障害にも対応しています。
脳卒中後、脊髄損傷後、外傷後の痙縮に対するボツリヌス治療やバクロフェン持続髄注療法も積極的に行なっています。
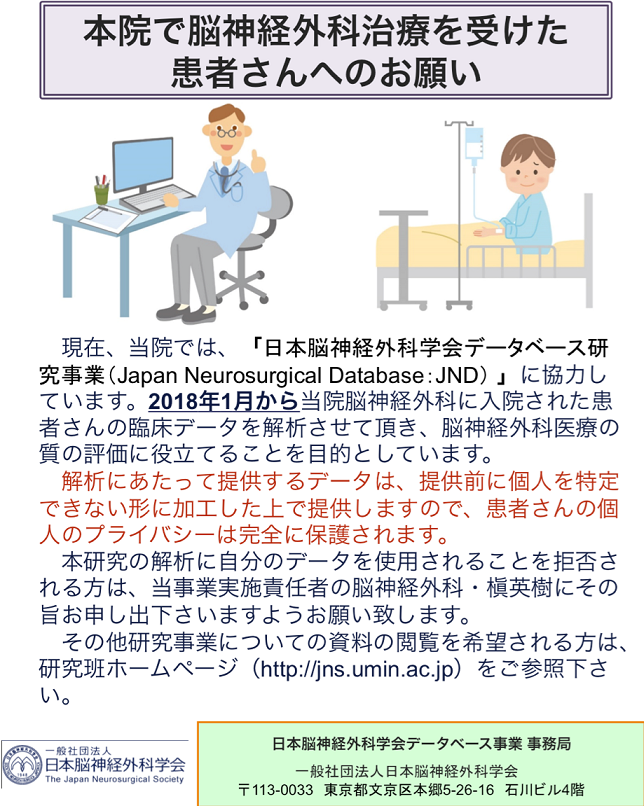
「一次脳卒中センターコア施設(PSCコア: primary stroke center)」に認定されました
当院は全ての脳卒中に対する急性期治療(治療、リハビリテーション、在宅/回復期リハビリテーション病院/療養型病院/施設への移行)に適切かつ速やかに対応可能な体制を整えており、2023年度10月に日本脳卒中学会より一次脳卒中センターコア(PSCコア:Primary Stroke Center Core)施設に西濃地区で唯一認定されました。
一次脳卒中センターコア(PSCコア:Primary Stroke Center Core)とは以下のような認定基準を満たしている施設です。
【認定基準】
一次脳卒中センター(PSC)コアは下記の5項目をみたすことが求められる
- 一次脳卒中センター(PSC)に認定されていること
- 日本脳神経血管内治療学会の脳血管内治療専門医と3学会認定の脳血栓回収療法実施医が合計して常勤3名以上であること
- 血栓回収治療実績が年間12例以上あること
- 自施設において24H/7Dで血栓回収治療に対応可能であること
- 脳卒中相談窓口を設置すること
・脳卒中診療
全ての脳卒中において適切な治療介入が出来る体制を整えています。脳梗塞については、超急性期治療(外科的治療、カテーテル治療、t-PA静注療法など特殊な治療)は脳神経外科が中心で管理を行い、それらが適応とならない保存的治療の脳梗塞については内科を中心に管理を行なっています。いずれの脳卒中においても治療管理はチームで管理し、早期にリハビリテーションを開始し、より患者さんの神経予後の改善が期待できるよう多職種で連携をとりながら管理を行なっています。栄養管理については管理栄養士や栄養サポートチームが介入しています。
脳卒中診療は治療だけでは終わりません。命が助かっても後遺症と向き合う患者さんが多く、周辺リハビリテーション病院や施設との連携、在宅支援、再発予防、障害認定なども重要となりますが、患者さんやそのご家族はどこに相談したら悩むことがあります。脳卒中相談窓口は、それら脳卒中に関連する様々な相談に対応する部署となります。当院ではよろず相談・地域連携課に設置しています。相談内容により、脳卒中療養相談士の資格をもった脳卒中専門医、脳卒中リハビリテーション専門看護師、医療ソーシャルワーカー、リハビリテーションスタッフ、薬剤師など専門の職種が対応します。特に脳卒中で入院中の患者さんには積極的に働きかけ、動画やパンフレットなど用いて再発予防や今後の流れをわかりやすく説明し、リハビリテーションスタッフが在宅での工夫や日常生活の中でのリハビリ方法などを提案しています。また、急性期加療終了後、円滑に在宅や回復期リハビリテーション病院/施設/療養型病院に移行出来るよう早期に医療ソーシャルワーカーが中心となり対応しています。



















